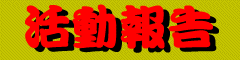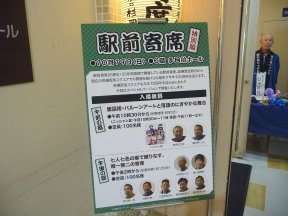|

|
会場の高槻阪急スクエアです。一昨年に
リニューアルされ阪急百貨店から阪急スク
エアに名称も変更になりました。JR高槻駅
の前ですが、お店は阪急ですのでお間違
えなく。天候は終日曇り空で、秋とはいえ、
まだまだ暑さが残っていました。
|
|

|
今回は、阪急スクエアの2周年なので、
特別編として午前と午後の二部構成です。
なので、私どももいつもより1時間早い
午前9時30分から設営準備を始めました。
客席の椅子については、阪急スクエア側の
方々に並べておいていただきました。
|
|

|
この会場で、午前からの寄席は開催した
ことがないので、少々不安もありましたが、
午前10時の阪急スクエアの開店と同時に
家族連れなどの多くのお客さんがお越しに
なられました。もちろん、いつもの「駅前
寄席」の常連さんもお見えです。
|
|

|
午前10時30分に第一部が開演。阪急
スクエア2周年のめでたい番組構成です。
まずは、高槻阪急スクエアのイベント担当
の方からご挨拶。 今回もくじらいだー@さ
んのブログを引用させていただいています。
(以下の青字の部分)
|
|

|
トップは、腹話術のニッシャン堂さんです。
F1腹話術グランプリで総合優勝され、
関西テレビの番組の「となりの人間国宝
さん」にも選ばれた実力派です。複数の
人形を一度に使い分ける腹話術は、見事
でした。バルーンアートも楽しめました。
|
|

|
左の写真が、いろんな人形が会話する
ニッシャン堂さんの腹話術です。
「一人で複数のキャラを演じ分ける」と
いう意味では、落語に通ずるものがある
ようですね。お客様へのサービス精神、
大いに刺激になりました。
|
|

|
さて、腹話術に続きましては、本来の
落語の寄席となります。一席目は、先月
の定例会でトリを務めた潮吹亭くじらさん。
演目は、「厄払い」です。昔、実際に
あった商売で、めでたい文句を並べたてて、
その家の災厄を払ってくれます。
|
|

|
ところが、この厄払いがいい加減な男で、
にわか仕込みで失敗ばかりです。
マイクの不備でやや聞き取りにくかった
ようで申し訳なかったのですが、理屈抜き
でおめでたい気分になれるネタであると
演者は勝手に思っています・・・・
|
|

|
二席目は、寿亭司之助さんです。演目は、
桂文珍師匠の創作落語「老婆の休日」。
といっても、オードリー・ヘップバーンや
グレゴリー・ペックは登場しません。元気な
お婆さんたちの病院の待合室での会話が
織りなす楽しい噺になっています。
|
|

|
直接、めでたいという言葉は出てきませんが、
長寿がテーマなので、めでたいと言えます。
司之助代表の「名刺代わり」とも
いえるおなじみの一席。この噺に出てくる
老婆たちの年齢に我々も近づきつつあり
ます。この元気さにあやかりたい!
|
|

|
第一部の落語のトリは、三流亭志まねさん。
演目は、「一目上がり」です。掛け軸の
ほめ方を教わった八五郎が、ほうび目当て
にいろんな家の掛け軸をほめに行くのです
が、ことごとく失敗!? どういう訳か、ほめ
言葉の数字が一目ずつ上がっていきます。
|
|

|
これこそ、タイトルどおり、言葉が上り調子
になっていく、めでたい落語だと言えます。
讃→詩→語、七福神からの芭蕉の句。
単なる「ダジャレ」ではない、どこか
高尚な香りのする一席ですね。
見事に午前の部をしめました。
|
|
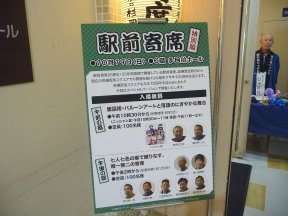
|
というところで、記念公演の第一部が
お開きになり、昼休憩の後、いつもの
午後2時開演の第二部に移ります。
今回は、特別編ということで、出演者の
写真の入ったディスプレイを設置して
いただきました。
|
|

|
|
![]()